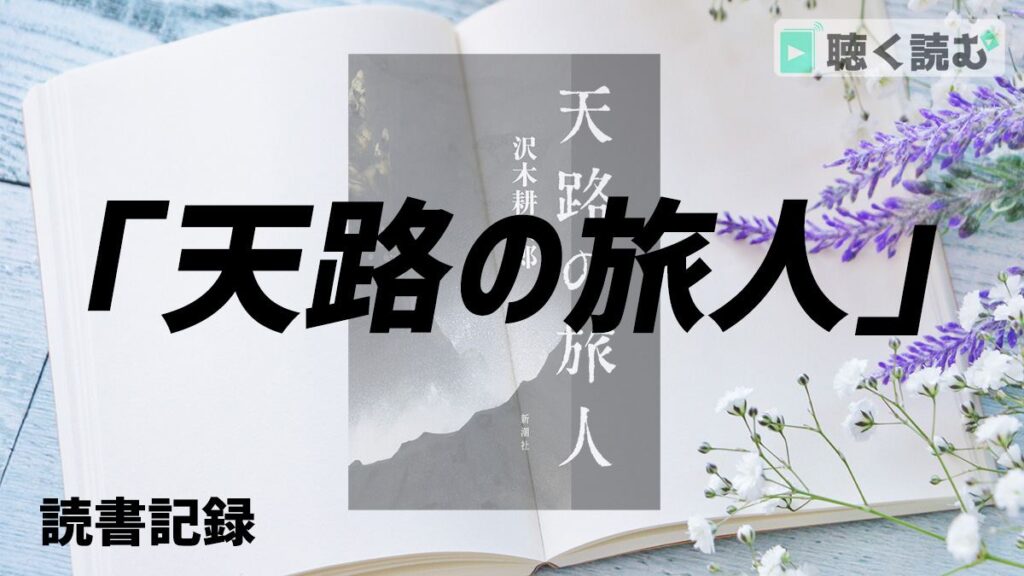
沢木耕太郎さん著『天路の旅人』を読ませていただいた感想および読書記録です。
登録は4ステップですが、失敗すると無料にならなかったり登録できません!失敗したくない方はこちら。
書籍情報と読書記録
『天路の旅人』の書籍は新潮社から2022年10月27日に単行本(四六変型)が2,640円で発売されました。2025年4月23日に文庫版の上巻(737円)、下巻(825円)で発売されています。文庫版には電子書籍もあります。オーディオブックは今のところありません(2025年7月現在)。
わたしは単行本の発売時に購入し、拝読させていただきました。
著者紹介:沢木耕太郎さん
著者は沢木耕太郎(さわきこうたろう)さんです。
1947年、東京生れ。横浜国大卒業。『若き実力者たち』でルポライターとしてデビューし、1979年『テロルの決算』で大宅壮一ノンフィクション賞、1982年『一瞬の夏』で新田次郎文学賞、1985年『バーボン・ストリート』で講談社エッセイ賞を受賞。1986年から刊行が始まった『深夜特急』三部作では、1993年、JTB紀行文学大賞を受賞した。(中略)・・・2023年『天路の旅人』で読売文学賞を受賞。ノンフィクション分野の作品の集大成として「沢木耕太郎ノンフィクション」が刊行されている。(新潮社より引用)
わたしは学生時代に友人に勧められたのをきっかけに「深夜特急」「一瞬の夏」「凍」「若き実力者たち」など沢木氏の著作を読み漁り、バックパックを担いでインド・ネパールを旅したのは、完全に「深夜特急」の影響でした。
「天路の旅人」のあらすじ
第二次世界大戦末期、中国大陸から鎖国されていたチベットに潜入した西川一三という旅人を描いた、長編ノンフィクションです。西川一三は日本軍の密偵として敵国である中国に潜入します。敗戦後も、西川はラマ僧に扮し、中国大陸を旅し続けます。帰国後、西川一三氏は自分の体験を「秘境西域八年の潜行」として発表しますが、その後は表舞台から姿を消し静かな人生を送りました。
本著作は西川一三本人の著作「秘境西域八年の潜行」(出版物だけでなくオリジナル原稿も含む)と、本人および関係者への取材をもとに、西川一三という旅人の輪郭が生き生きと浮かび上がっています。
ちなみに「天路」は「てんろ」と読みます。
「天路の旅人」の感想(ネタバレあり)
圧倒的な旅
わたしは西川一三という人間について、これまで全く知見がありませんでした。そんな人がいたということすら知らない、まったくの白紙の状態で本著を読み始めました。
そしてまず第一に圧倒されました。この西川一三という男の超人的とも言えるこの旅に。読む前はこれほど夢中になるとは思っていなかったくらい、ワクワクしながら熱中して読みすすめました。バックパッカーのお気楽な旅とは比較にならない、使命をおびた旅。しかし西川はつらいなかでもいろんなことを吸収しながら、旅のスキルを高め、自分の知らない新しい土地、新しい世界をみることに楽しみを見出していきます。
それは、こんな旅を自分もしてみたいなどとは軽々しくとても言えないような凄まじい旅です。とても真似なんかできない。真似したくないのではない、とても真似ができないような想像をはるかに超えてた圧倒的な旅でした。
西川氏の強靭な体力もさることながら、西川氏の人柄がまたすごい。至誠の心を大切にする誠実さ、心配り、周りの人から信頼され慕われる様子、リチュ河で自分の危険を顧みず一行のピンチを救おうと思った気概、世話になった人たちへの感謝の思いからのさまざまな行動など、西川一三という人物の魅力にもとても惹かれました。
その根底にあったものは、吉田松陰が説いた「至誠の心」でした。「至誠」とは孟子の教えで「至誠にして動からざる者は未だこれ有らざるなり」というもので、「まごころを極めること」「誠の心を尽くすこと」を意味します。西川一三氏はまさに「至誠の心」を体現したような人でした。
西川氏の信条にはもう一つ重要なものがありました。それは「食べるものがあり、寝る場所があるという最低限の生活で人は幸せを感じることができる」というものでした。言葉で言うのは容易いが、西川氏はこの言葉どおりの旅をし、また日本に帰ってからも、この言葉どおりの人生を送ったのだろうと想像します。
西川氏の人生という旅に圧倒されない旅人はおそらくいないだろうと思います。
物足りないさ
しかし一方で「物足りなさ」を感じてしまいました。
西川氏の旅は突如、本人も望まない形で旅は中断されてしまう。あっけなくも旅が中途半端に終わってしまったことからくる物足りなさは、この本の読者なら皆感じるのではないだろうか。しかしわたしがより強く物足りないと感じるのは、西川氏のその後である。
西川氏が本当になりたかったのは、蒙古高原を自由に駆け回る馬だった。あの馬たちのように、自由に旅がしたかったのだ。もしも西川氏が蒙古高原を自由に駆け回る馬になる努力をし続けたら・・・もう一度あの旅の続きをすることにこだわっていたら、きっといつかは行けたのではないだろうか。
でも彼は汗をかきながら荷を運ぶ馬のような、地道な地に足のついた人生を選んだ。そこには後悔の念のようなものは見受けられない。1年364日、元旦以外休みなく働き続けるラマ僧の修行のような生活を日々を淡々と送リ続けた。
しかしわたしは想像する。あのとき突如旅が中断されてしまってから、最期のときを迎えるまで。何度も何度も夢想したのではないだろうか?あのときあの旅が中断されなかったから・・・木村氏が一言相談してくれていたら・・・と。それこそ何十回、何百回と考えずにはいられなかったのではないだろうか。ビルマ、シャム、アフガニスタン・・・まだみたことがない新しい世界を
幸せとはなんだろうか?
彼はその後の人生でもう一度旅に出ることなく、汗をかきながら荷を運ぶことを選んだ。
静かな生き方に対する憧れ。寝る場所があり食べるものもあり仕事もあり、最低限生きていくためのものは足りている。多くを求めず、淡々と静かに日々の暮らしの中に小さな楽しみを感じながら生きていく。そこに幸せを感じることができることが、本当の幸せなのかもしれない。
ちょっと物足りないけれど心は足りている。そこが稀有な旅人がたどり着いた「幸せ」という場所なのかもしれない。
最後の言葉
最後の言葉というのは正確ではないが、西川氏が最後に家に立ち寄ったときに娘さんに言った言葉。
「もっといろいろなところに行きたかったなぁ」
自分の最期を予期していた西川氏が、心の奥底にしまっておいた想いがふっと出てきのではないだろうかと想像します。
西川氏は蒙古高原を自由に駆け回る馬にはならなかった(あるいはなれなかった)が、本当はそういう馬になりたかった、あのとき中断することなく自由に旅がしたかった。もう一度旅に出たかった。そう考えるとこの言葉は本当に切ない。
「こんな男がいたということを、覚えておいてくれよな」
その西川氏の想いに応えたのがこの「天路の旅人」という本なのだと思う。
その言葉通り、西川一三という稀有な旅人は沢木耕太郎の手で、この本を読んだすべての旅人の魂に刻まれたのではないだろうか。少なくともわたしはこの旅人のことを忘れない。
関連著書
西川一三著「秘境西域八年の潜行」は芙蓉書房版、中公文庫版ともに古本屋・フリマアプリ等でもなかなか手に入れることは難しいようですが、中公文庫版の電子書籍(全6巻)があります。
ままた西川氏とほぼ同時期に同じような潜行旅をし、途中行動をともにする時期もあった木村肥佐生氏の著書「チベット潜行十年」「チベット偽装の十年」もあります。
まとめ
旅が好きな人、チベットやインドに興味のある人はハマると思います。人はなぜ旅に出るのか?幸せとはなんなのか?そんなことを考えさせられる一冊でした。
旅人のバイブル、沢木耕太郎著「深夜特急1-6巻」はオーディブルの聴き放題で聴けます。
登録は4ステップですが、失敗すると無料にならなかったり登録できません!失敗したくない方はこちら。
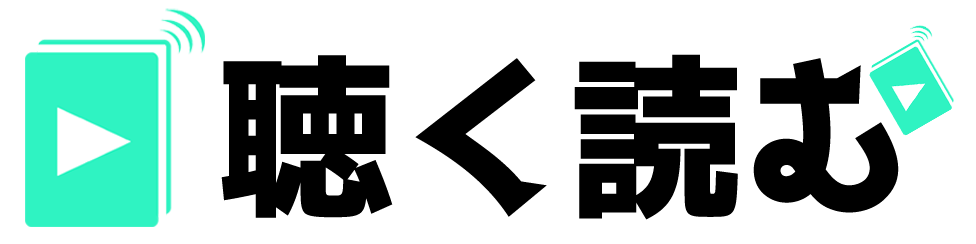
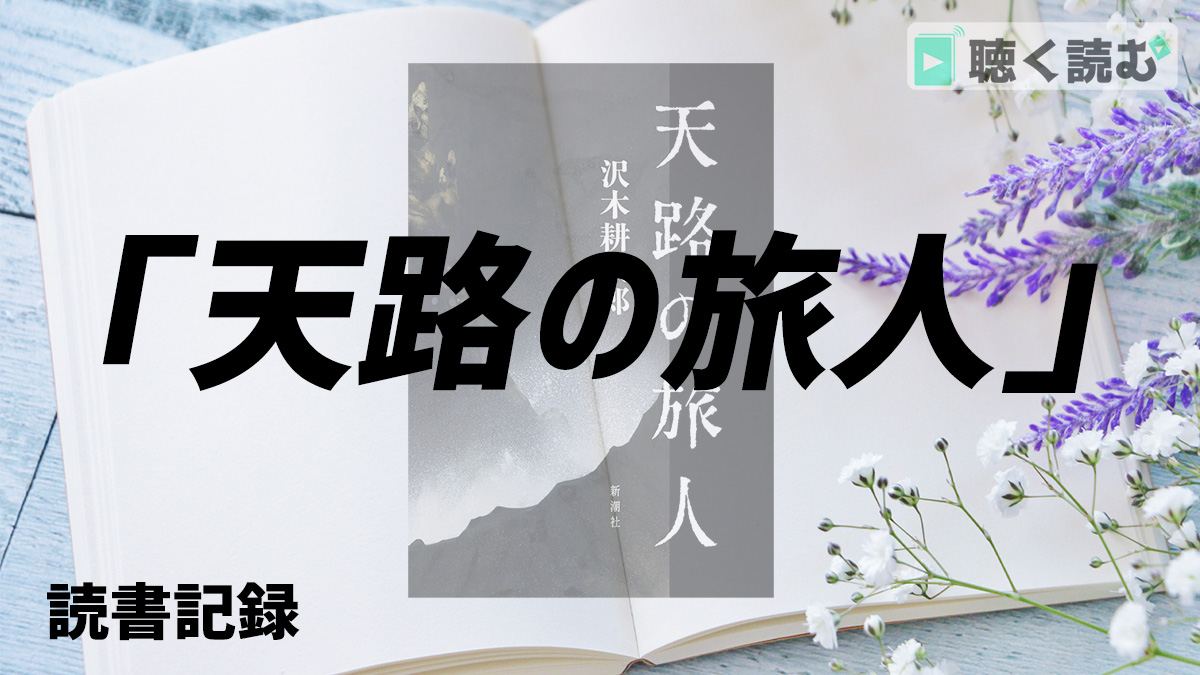
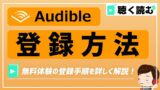






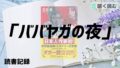
コメント