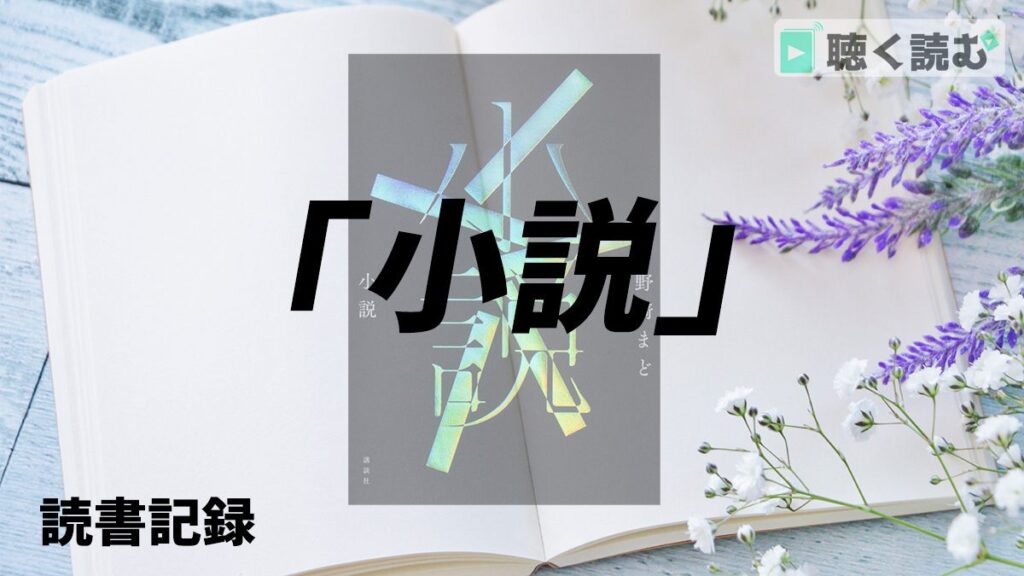
2025年本屋大賞3位!野崎まどさん著「小説」を読ませていただいた感想および読書記録です。わたしの中では2025年本屋大賞はこの作品でした。
現在 Audible は対象者限定で 3ヶ月 月額99円キャンペーン を開催中です(2026年1月29日まで)!再登録の方は 3か月50%OFF が適用される場合があります。 ※リンク先にて確認できます。
登録は4ステップですが、失敗すると無料にならなかったり登録できません!失敗したくない方はこちら。
書籍情報と読書記録
書籍は講談社から2024年11月20日に発売された書き下ろし作品です。単行本(四六変型)、電子書籍ともに2,145円です。
わたしは2025年4月に単行本を購入し拝読させていただきました。その後電子書籍も購入しました。単行本を持っているのに、さらに電子書籍を購入する理由は、電子なら検索ができるので部分的に読み返したり、目的の記述を探すのに時間がかからないためです。最初から電子書籍のみでもよいのですが、「読書意欲が駆られる」という理由で1冊目は単行本で読むことが多いです。オーディブルがある作品は、最初は耳で聴くことも多いです。
ただし「小説」を含め野崎まど作品は1冊もオーディオブック化されていません。これは出版社や著者の方の方針なのかもしれません。
わたしは「野崎まど作品のオーディオブック化」をオーディブルのカスタマーサービスに要望しておきました。そういう声が多ければ、いずれはオーディオブック化もありえるかもしれません。
著者紹介:野崎まどさん
著者は野崎まど(のざきまど)さんです。
Wikipediaによると、2009年、投稿作「[映] アムリタ」で、「メディアワークス文庫賞」の最初の受賞者となる。2013年の『know』は第34回日本SF大賞候補作品、2021年、『タイタン』で第42回吉川英治文学新人賞候補。2025年、『小説』が第22回本屋大賞3位を獲得とあります。
この「小説」が野崎まど作品の初見本でした。映像ではアニメの「正解するカド」を観てました。今までのアニメにない斬新さ、政治的な社会性もあり、人間とは?進歩とはなんなのか考えさせられたのを覚えています。もっとも野崎まど氏が脚本を担当していたことを知ったのは「小説」を読んだあとでした。
「小説」のあらすじ
- 内海集司(うつみしゅうじ)…主人公。読書好き。
- 外崎真(とのさきまこと)…本を通して内海集司と親友になる。
- 髭先生(ひげせんせい)…小説家。
- 佐藤学(さとうまなぶ)…内海と外崎の小学校時代の教師
- 寄合則代(よりあいのりよ)…内海と外崎の小学校時代の教師
- 孫(まご)…謎の少女。
小説を読むのが好きな少年内海集司(うつみしゅうじ)は、12歳とき図書館で外崎真と出会う。二人は小説の魅力を共有できる生涯の友となる。あるとき学校の近くの小説家が住んでいるというモジャ屋敷に潜り込み、小説家の髭先生と出会い、二人の小説世界はさらに豊かになる。
やがて外崎は小説を書くことにも喜びを抱くようになる。一方の内海は読む専門であり書くことに興味は持てなかった。そのことからいつしか二人の間には溝のようなものが生まれていく。そして決定的なことが起きてしまう。
人はなぜ小説を読むのか?書くのか?小説を読むだけではだめなのか?
その答えがここにあります。
「小説」の感想(ネタバレあり)
まずは読後の感想ツイートから。
小説を読む後ろめたさとは?
この物語は二人の本好きが出会い、無二の親友となっていくことから始まる。小説を読むのが好きな少年内海集司は、外崎真と出会い、本を通して親交を深めていく。内海は読む専門だったが、外崎は小説を書く方にも目覚めていく。
内海集司は子供の頃、本を読むと父親が喜ぶことを発見し、親の喜ぶ顔をみたい一心で本を読むようになる。しかし成長するにつれ、いつしか本を読んでも父親は喜ばなくなる。
子供の頃、本が欲しいというと親が喜んでくれた経験は、わたしにもある。読書をしていると、勉強するのと同じくらい親は喜ぶのだ。読書は勉強より面白かったし、親が褒めてくれるのがうしくて、ますます本を読むようになった。
しかし親が喜んでいたのは小学生までだった。中学生になり、わたしの読む本が課題図書や文学から、SFやファンタジー、推理小説に移っていくにつれて、わたしが読書をしても親は喜ばなくなった。どちらかというと批判的な視線を感じるようになってきた。マンガを読むよりはマシだが小説を読むより勉強しろ!というプレッシャーを感じずにはいられなかった。こうして内海集司と同じように、わたしも小説を読むという行為にある種の後ろめたさのようなものを感じるようになっていった。
大学生の頃は時間もあり、親の目も届かくなり、一番自由に小説を読めた。それでもこんなことがあった。就職活動をがんばっていた友人と、留年が決まっていたわたしの間で、あるときこんなやり取りがあった。
友人「最近どんな本読んだ?」
わたし「村上春樹のねじまき鳥クロニクル」
友人「・・・それって今のお前の人生にとって何かの役に立つの?」
わたしはちょっと面食らってしまった。今にして思えば、就職活動に忙しい友人はもっと自己啓発的なものだったり、自分への投資になるような本だったりを期待して、参考にしようと思って聞いたのだろうと想像はつく。あまりにも期待外れの答えだったからこそ、この返しだったのだと思う。
ある種の人にとっては、小説を読むことは「悪いこと」「無駄なこと」なのだろう。
しかし社会人になると、仕事の忙しから小説から遠ざかってしまい、自分にも同じような考えが生まれてきてしまう。小説を読んでる時間がない、小説を読む時間があったら、仕事関係の本を読んだほうがいいだろう、と思うようになっていた。
中学生の頃に芽生えた「後ろめたさ」とは意味合いが変わってきたが、やはりこれも「小説を読むことの後ろめたさ」と言えるだろう。
小説を読む意味とは?
小説を読む後ろめたさには、「小説を読む」ことよりも「勉強」や「仕事」の方が重要という考えがあるだろう。それは「小説を読む」ことは娯楽であり、エンターテインメントだからである。このことについてわたしは何の疑いも持っていませんでした。だから、小説を読むのは、自分が小説を読みたいから読むであって、小説を読むのが好きだから読むのです。それ以上の理由があるとは考えてもいませんでした。
つまり
「小説を読むことにに意味なんかない」
と思っていたし、そう思っている人は多いのではないでしょうか。
しかし、この物語は「小説を読む」という行為に意味付けをしてくれくれます。
では「小説を読む」という行為にはどんな意味があるのか?ざっくりいうとこんな感じである。
それは宇宙の成り立ちから始まる。宇宙には集合して秩序化する流れがある(エントロピーの法則の逆)。集まったものは内側になり、集まっていないものは外側になる。内と外という境界ができる(内海と外崎という名前はこのメタファーなのだろう)。外から見えない、内側に内包された性質とは「意味」である。世界は集まって意味を増やしている。そして人は嘘を使って無限に意味を増やすことができる。それがフィクション=小説である。だから・・・
この文章だけ読んでも、よくわからないだろう。
これを詳しく丁寧にしかも息をつかせぬ面白さで解説してくれるのが、この「小説」という物語である。
わたしはこれまで、小説を読んでこれほど幸福感に満たされたことはありませんでした。「そんな壮大な意味があったのか、すごい!」という驚きと感動があります。
すべての本好き、小説好きを全肯定し、やさしく抱きしめてくれる、そんな小説です。わたしの中では2025年本屋大賞はこの作品でした。
興味を持った方はぜひ、野崎まど著「小説」を手に取ってみてください。
「外崎真」と「野崎まど」
ここからは蛇足です。
ふと気づいたのですが。
「外崎真」と「野崎まど」、字面は全然異なるが、ひらがなにしてみると「とのさきまこと」と「のさきまど」。
「とのさきまこと」の「と」「こ」を除くと「のさきまと」になるのは偶然ではないだろう。
「外崎真」は「野崎まど」自身なのであろう。
「小説」というタイトルについて
少しうろ覚えですが、BSテレビ東京の「あの本、読みました?」で、担当編集者の方が「小説」というタイトルについて、野崎先生にこのタイトルはもう少しなんとかならないか?と相談をしていたという話を語られていました。
「小説」というタイトルがあまりにも一般的な言葉だからという理由です。「小説」というワードで検索しようとしても、一般的な言葉過ぎて埋もれてしまうからです。野崎先生は「この本は小説について書いたものなので、やはり小説というタイトルがふさわしい」と考えを変えられなかったそうです。
ちなみに2025年5月21日現在、Googleで「小説」と検索すると、第1位に表示されたのは以下のサイトでした(現在は違います)。
一時的ではありましたが、この一般用語での1位はすごいことだと思います。
表紙絵の意味

この「小説」という本の表紙はキラキラしていて見る角度によっていろんな色に見えとても印象的です。タイトルが一般的な用語だけに、表紙を派手にしたのかなと勝手に想像しています。
そしてわたしが注目したいのは、小説という文字に重なるように描かれた5つの細長い長方形です。これは何を表しているのでしょうか?
ネットで検索しみましたが、この表紙絵の図について言及している情報は見つかりませんでした。
本を読む前は人の形か、あるいは本を表しているのかな?と思っていました。「小説」の最後まで読み終わった後にあらためてのこの表紙絵をみると、この輝く長方形の絵は「恒星のように輝く1冊1冊の本」を表していることがわかります。
しかし疑問が残りました。本を表すにしては何か変な気がする・・・なぜこういう配置なのだろう?と
それから少し時間がたちました。表紙絵のことなど頭からなくなりかけていたときに、ふと立ち寄った本屋で「小説」の表紙が目に入りました。そのとき、虹色に反射する色と相まって表紙の「小説」という文字に重なるように「ある生き物」が見えたです。
一度そういう風にみるともうそうとしか見えません。それはこの「小説」という話にも出てくる生き物です。
そう
わたしが、この表紙に見たのはキラキラ光る「妖精」でした。
まとめ
わたしの中では2025年本屋大賞はこの作品でした。すべての小説好きに、ぜひ届いて欲しい作品です。
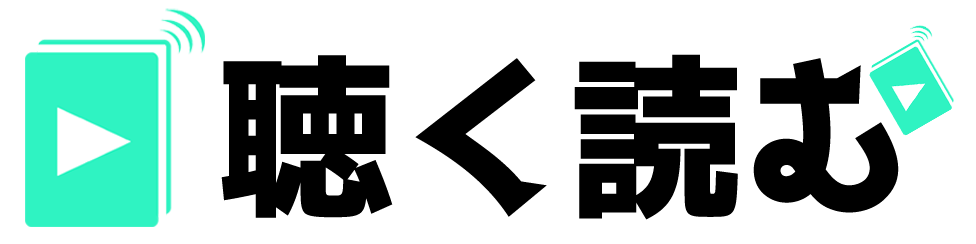
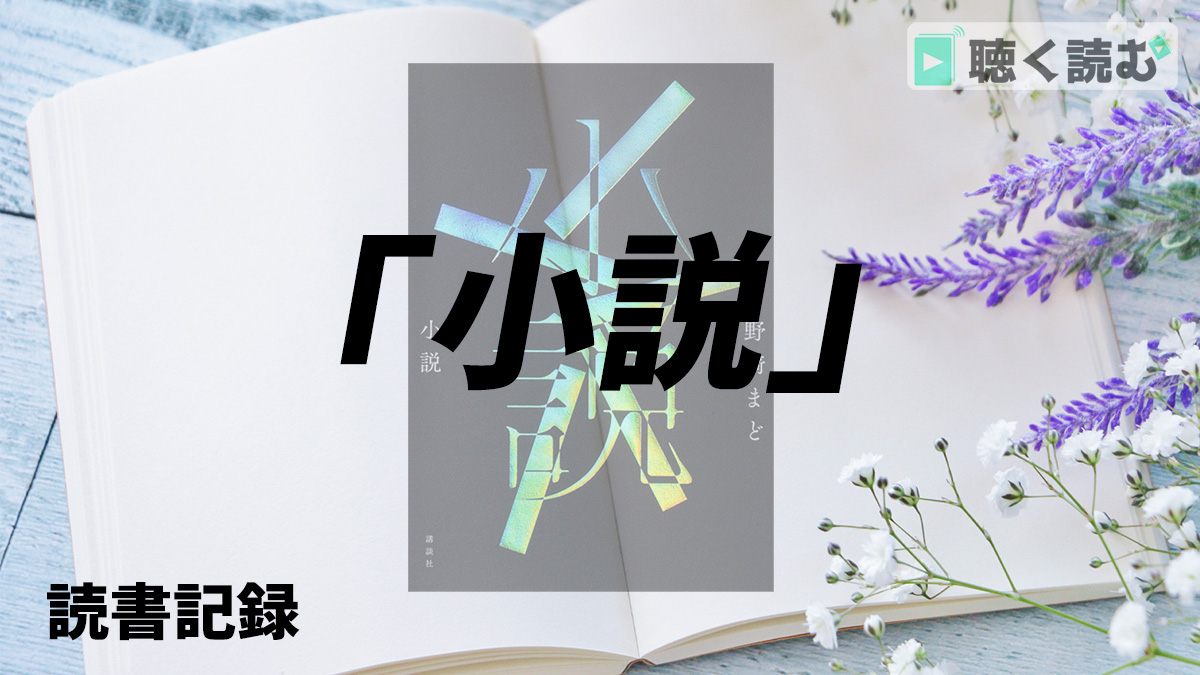
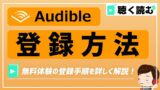


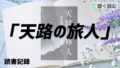
コメント